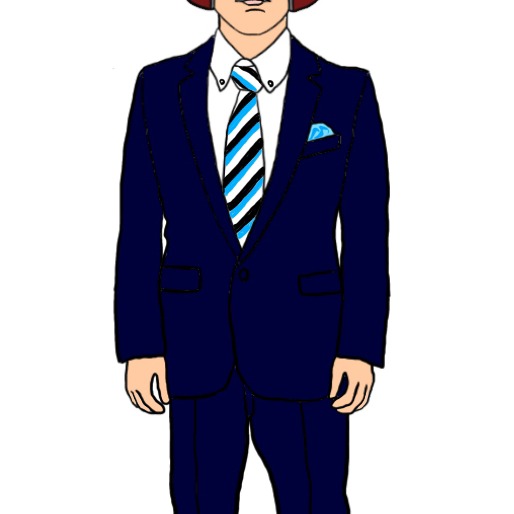いわごん
10 件の小説明るいものが読みたいと言われても
明るいものが読みたいと言われても困る。また担当編集に言われてしまった。 「世間はカラッとしてて読みやすいものを求めてるスよ。純文学とかって今売れないじゃないですかぁ。マミさんも、もっと明るい経験増やしたほうがいいと思うんすよね~。」 「はあ。」 「彼氏とか作って遊んじゃいましょ!旅行代は経費になりますよ!」 「あんまり彼氏とか要らないっていうか…」 ここまできてようやく察したのか、担当編集は眉間をピクリと震わせて 「まーまー、今日は飲みましょ!期待してますよ!先生!」 ニコニコしながら持っていたグラスを一気に飲み干し、ハイボールを二つ頼んだ。彼は一橋大学を卒業して十三年間ずっと編集の仕事をしているという。こんなことがしたくてこの世界に入ったのだろうかと思う。それは私もそうなんだけど。 饒舌に話し続ける彼に適当に相槌を打ちながら、飲んでも飲んでも出てくる酒にのまれて穏やかに記憶が飛んでいった。 起きたらケバい天井とうっすらと香水の匂いがしてラブホテルにいると気づいた。 「飲みすぎた…」 きっとベロベロになった私を担当編集が連れてきてくれたのだろう。前にもこんなことがあった。その時にもう二度と酒は飲まないと誓ったのに。 さっさと出よう。もう街ごと消えてなくなりたい気分だ。 遠くの椅子に置いてあったかばんを見つけ、ひったくるように取った。 ドアにも天井と同じ気持ちの悪い模様が刷り込まれている。吐き気を抑えつつ外に出た。 エレベータを待っていたら男女の会話が聞こえてきた。女が男を気遣う声が聞こえる。ズルズルと服か何かをする音が近づいてくる。 隣まできたカップルは男が女に支えられていた。彼女さん大変だなとぼんやり思っていたら、小気味のいい到着音が鳴った。 乗って「開」を押して待っていた。「乗らないんですか」と若干苛立ちながら顔をあげると、目の前に担当編集がいた。私より少し綺麗な人に肩をあずけながら。 本当に驚いた時、人は声が出ない。その発見を喜ぶ反面、私自身は突然訪れたその状況に窮していた。彼は急に顔が若返って大学生みたいになっていた。 「バカ」「なんで」「好きなのに」「私じゃダメだったのか」「大嫌い」「担当変えて」色々言いたいことはあったが、それ以上にこの場から離れたい気持ちが勝った。 「閉」を押そうと手を伸ばしたら、 「明るいの!お願いしますよ!」 それまで黙っていた彼がバカでかい声で言ってきた。 閉まる扉の向こう側にニコニコしたいつもの彼がいた。さすがにもう女の肩は離していた。 本当に大嫌いだ、そういうところが。 重力に引っ張られ、落ちていく私の頭の中で次の話の構想が高速で練られていた。
誰か
実は雪だるまなんて作ったことない。秋田出身なのに周りはみんなヤンキーばっかりだったせいで思うようにはしゃげなかった。同世代が当然のように高校を中退していく中で冴えない脳みそを振り絞って東京の大学に合格した。友だちはいなかったけれど、東京にいけば全てが変わると思っていた。合格した日の夜、コンビニで「ピースとハイライトをください」って言ったら2種類出てきて焦った。サザンの影響で初めてのたばこはピースとハイライトにしようって決めていたから。でも2つ出てくるなんて聞いてない。ひどいよサザン。結局ハイライトに火を点けて1人祝煙?をあげた。これからサザンのライブにも何度も行けるって信じてた。雪道はすぐに投げたヤニカスを呑んで黒くなった。 結局今になってもサザンのライブには行ってない。うだつの上がらない生活を続け気づいたら就職戦線で途方に暮れていた。親には今年は帰らないと連絡したっきりだ。電話もしていない。サークルの引退ライブに出るかまだ迷ってる。もう2ヶ月ギターを触っていない。昨日の面接が通っていたらいいなと思う。けっこう面接官のおばちゃん俺のこと気に入ってそうだった。 ぼさぼさ頭のままベランダで煙草を吸う。もう13時半であることにイライラする。昨日から雪が降り続いていて肌寒い。静かだ。アパートと公道の境界線にちんまりと雪だるまが作ってある。 「そうやってかわいげだけで生きていたいよ」 言ってみたら沈黙が深すぎて恥ずい。ピロリロと携帯が鳴った。開いたら昨日の面接のお祈りメールだった。うざい。もうとにかくイライラしてNHKでも襲っちゃおうかと訳の分からないことを一瞬考えた。で次の瞬間には雪だるまに向かってヤニカスを投げていた。大分手前に落ちたそれは東京の雪上ではいつまでもそのまま残っていて、その後数日にわたっておれの良心を咎め続けた。
グラタンメンタル
学生時代、ファミレスでアルバイトをしていた。接客は自分には向いていた。大学では友だちに恵まれず、細々と学校で過ごした鬱憤を晴らすように笑顔を振りまいていた。昼のシフトで入ると決まってパートのおばちゃんに可愛がられた。呼び出し音が鳴ればテーブルに駆け付け、注文を取り厨房に渡す。慣れると機械的に体は動いた。 3年目になると仕事だけでなく受け答えも定型化してくる。世間話も同じことを話す。それは染みついて離れず、他の言葉を探そうとすることもできない窮屈な感覚だ。だけどなんてことはない。そこに安心感を感じるのがおばちゃんたちだ。これが正解だと自分をなだめ続けた。 4年目でもう少しでアルバイトを辞めるころ、40代くらいの夫婦とおぼしき客を対応した。人のよさそうな顔で高級ではないけれど品の良いシャツを着ていた。グラタンとスパゲッティを届け、帰った後で男性がいた席を見やるとグラタンがぐちゃぐちゃに踏みつぶされていた。さっきの人の席かどうかもう一度確認したがやはりさっきのお客さんだった。うちはバルじゃないのに。 拭こうとして見るとテーブルの足と床の隙間に追いやるようにグラタンは挟まっており、拭くのは一苦労だった。ここまできて、もしかしたらさっきのお客さんは夫婦じゃなかったのかもしれないと気づいた。女性にこぼしたグラタンを見られたくなかったのか。拭くのも嫌だったのか。それともその会話になることを嫌ったのか。でも「大丈夫ですか、足元拭きますよ」って言っても変な感じになったら嫌だしなあ。何かできたかなあ。 パートのおばちゃんには黙っていた。きっと興味ないから。 最近、友だちが自殺未遂をした。年に2回くらいは会うし、仲の良い方だと思っていた。話を聞くと職場の悩みがあってアルコール依存症になっていたらしい。全く知らなかった。早くに教えてくれたらとは思うけれど、その葛藤を理解することは難しかっただろう。結局その人がなぜグラタンを踏みつぶすに至るのか、聞けないままだ。どこかに他の選択肢があったんじゃないかと思っても、思うことしかできず自分の無力さを痛感した。ちゃんと向き合えていたら違ったのかな。グラタンも友だちも。 とりあえずパートのおばちゃんからのラインを定型文で置きにいくのを辞めた。もっとこうなんていうか、柔らかく熱くいきたいから。
冬至
今日冬至ですね 日の出てる時間が一番短いらしいですよ かぼちゃ食べなきゃ あぁかぼちゃ…買ってないなあー ゆず湯入ります? 入らないよ そうですよね。なんだかんだそんなものですよね うん。入らない もう1日が終わってしまう。来年も話していられたらいいのにね。
メルカリ
メルカリで教科書を買った。生協で買うと10%引きだが、メルカリだと大体半額以下で買えるので愛用していた。今回は2500円の教科書を700円で落札した。 同じ教科書を使っている人はまあ同じ大学の誰かだ。だから毎回変な気持ちになる。この大学にいる見ず知らずの、あるいは知り合いかもしれない誰かから教科書を買っているのだ。アプリの力ってすごい。 届いた教科書は綺麗でほとんど未使用に近い。ラッキーと思っていると教科書からひらひらと何かが落ちた。拾い、読んでみると小さな丸文字で「ありがとうございます😊機会があればまたよろしくお願いします❤️」と書いてあった。 顔が真っ赤になり体中を気力が駆け巡った。生まれて初めての女性からの手紙だ!恋だ!恋が始まってしまったのだ! このままこの教科書を学校に持っていけばきっと彼女に会える。たまたま大教室で教科書を読んでいたら「あれ?それ私の教科書じゃないですか?」と声をかけられる。信じられない出会い方だが、現実は時に脚本を超える。彼女はその文体に似つかわしい気遣いのできる人だった。それがきっかけで毎週授業を一緒に受けることになると、徐々に親交を深めていく。山場のテストを乗り越えたタイミングで「お疲れ様会」に彼女を誘う。2人で夜の街に繰り出していってそれから…。 「迅速に対応していただきありがとうございます。機会があればまたよろしくお願いします。」このメッセージが第一歩だ。礼儀正しく。第一印象は大切だ。確認して送信ボタンを押した。もう一度紙を見る。何度見ても愛おしい。一番お気に入りの硬派なエッセイにそっと栞代わりに挿した。 昔の日記を読み返すのはしんどい。大学の頃、相当暇だったということだけが分かった。今よりこの頃のほうが幸せではあったのかもしれないな…。そうやって少し感傷に浸りながら、栞をはさみ日記を引き出しの一番奥にしまった。
最近好きな曲の話
今更だけどKID FRESINOとC.O.S.Aがキテる。 FRESINOは8月のフジロックで見てから本格的にアルバムを聴いている。それからずっと魅せられっぱなしだ。中でもC.O.S.Aとの共作である「Somewhere」がいい。 このアルバム制作時、KID FRESINOはニューヨークに住んでいた。当時23歳である。FRESINOといえばそのスタイルやファッションセンスは2021年でも一目置かれている。一方でC.O.S.Aは1987年生まれ、名古屋の知立市で生まれ育ちそこで働いている。その見た目からはマッチョさと男気を感じさせる。ヒップホップはその人の生き様が少なからず反映されるとしたら2人の線は全く重なっていないように思える。それなのにこのアルバムの親和性は非常に高い。何がここまでこの2人を結び付けているのだろう。 何度も曲を聴くうちに1つの仮説を思いついた。2人とも相反する側面を持ち合わせている。 俺の大好きな曲「Swing at somewhere feat.コトリンゴ」を引用したい。「Premiumな夜 sing a song floor彩る アスファルトこびり付くgumはお前よりも街を知ってる」floorから想起されるVIPな床からアスファルトのガムへと一瞬でワープする。しかし、だからこそガムのたくましさは際立つ。「ハハ 笑えるくらい陽気な人生は程遠いが ナイスな夜だけは忘れたくねえんだ」ふと本音が垣間見えた気がする。密かな諦念と至上の喜びが合わさる。jazzyなビートからは大人の、あるいはFRESINOの住む海外の香りがするが、実は歌詞の人はリアルな現実を、2:8くらいで大変さが勝つ人生を過ごしている。理想と現実に焦るFRESINOとどこか余裕を感じさせるC.O.S.A、それをアンニュイな雰囲気でコトリンゴのhookが中和させている。様々な階層で相反する何かが、中和しているのだ。 FRESINOは最新アルバムのインタビューでネガテビティーが創作の原動力でありつつ、そのなかで些細な幸福を心から感じてしまうアンビバレントな心境があると答えている。「Somewhere」ではそうしたネガテビティーが質の高い音にのりつつ絶妙なバランスで保たれている。そしてそれはネガティブでありつつ鬱屈ではない。C.O.S.Aは俺たちをこうも誘っている。 「勤勉で出来る限り善良で 気遣いのある人たちは踊ってくれ peace 傷を負い罪を背負ったその体で いつも孤独を引きずる人も加わってくれ」
敗者、さば缶
残業で今日は帰りが遅くなった。もう23時なのでコンビニで適当に飯を買ってくことにした。 店には活気がなくマガジンを立ち読みしている客とダルそうに品出しをしている外人の店員が2人いるだけだ。 ほんの少し期待して弁当のコーナーに行ってみたが、ロングサイズの納豆巻きが3本と鱒寿司のおにぎりが1つしかなかった。誰が長い納豆巻きを好んで食べると思ったのだろうと、コンビニの商品開発部にマスクの下で悪態をつく。 仕方がないのでレトルトのコーナーに行った。「鯖缶」と「つぶ貝缶」と「はごろも煮の缶詰」しか残ってない。絶望し、発狂しそうになったが何とか思いとどまった。 急に下から3つの缶詰ドラフト会議になり悩む。はごろも煮は無いとして鯖かつぶ貝だ。味は同じくらい好きだけど鯖のほうが栄養面で若干上かもしれない。 「やれるかお前」「頑張ります」 一言交わし腹は決まった。さば缶を手に取り、レジに向かう。 慣れた作業で店員はレジを打つ。 「160円です」 俺はくしゃくしゃの財布の奥から何とか小銭を取り出そうとする。すると、手間取る俺を横目に店員はがらがらの棚に輝かんばかりのホットスナックを追加しだした。 「えっ」 思わず声が出てしまった。店員に不審そうに見られ焦ったが、こんなチャンスを無駄にはできない。 「唐揚げ3つとポテトフライください」 「合わせて960円です」 「あとこれいらないんで戻しといてください」 「えっ」 「戻しといてください」 「はい。800円になります」 下から聞こえる声を無視して千円札を取り出す。 資本主義。競争の厳しい世の中である。仕方がない。 熱々の唐揚げを店に出てすぐに頬張る。 「うまっ」 思わず声が漏れる。今夜、勝ったのはどうやら俺みたいだ
音読
小学生の頃、僕は絵に描いたような真面目ちゃんだった。 無口で人とあまり喋らず、黙々と勉強することが唯一の正義だと信じて疑わなかった。 宿題を忘れたら気が狂うくらい自分を責めていたし、担任の先生に書くよう促された「今学期の目標」に、自ら「克己」と書いたことを今でも覚えている。 そうした過剰な規律はある程度まで自分を引き上げることをしてくれるが、望まない努力は同時にある種の不安定さを心に育ててしまったように思う。 そんな中でも物語の授業だけは好きだった。 登場人物の心の機微を拾い、言語化する作業は機械じみた日本の教育の中でまだ手触りがあった。 特に得意だったのが音読だ。 どのクラスにも1人、普段無口なくせに、授業中はきはきしゃべる浮いたやつがいただろう。 それが僕だ。 でも、どれだけクラスで浮こうが友だちに煙たがられようが関係なかった。 あくまで僕の目標は「克己」だ。 音読も気持ちを込めてうまく読んだほうが点は高くなるし、評価は上がると信じていた。 「ねえ、あんた学校は大丈夫なの。」 急に母から尋ねられ、ごにょごにょした音が口から漏れた。 動揺は急速に上がる心拍数にしっかりと表れていた。 「いいから。もう読むから聞いて。」 無理やり丸め込むように音読の宿題に移った。 これ以上学校の話をしたくなかった。早く今日の課題を終わらせたかった。 母の姿が目の端に映らないよう少し伏し目がちに、題材である「ちいちゃんのかげおくり」を読み始めた。 戦争の悲惨さ、ちいちゃんの純真さ、家族を想う気持ち。 些細な切れ目や行間にも注意を払いつつ、読み進めていく。 「ゆっくり、ゆっくり、悲しみを込めて」 教科書のメモにそう書いてある。 もうすぐ「とお」数え終わり、ちいちゃんが空を見上げる。 「ちいちゃんのかげおくり」は今日も成功し、僕は顔をあげた。 母は静かに泣いていた。 ティッシュで顔を覆っていたが、その隙間を抜けた線は整った化粧をまばらに崩していく。 小学生にとって親が泣いている姿ほどショックなものは無い。 僕も確かにショックを受けていた。 しかしこういう時にどうすればいいのか、その答えを持ち合わせてはいなかった。 おずおずと近づくと「大丈夫?」と声をかけた。 返事は無かったが、母は小さく頷いた。 「これ。」 まだ嗚咽が残る中、僕は音読カードに判子を押すよう催促した。 「ああ。ごめんね。」 強く押したせいでインクが淵から染み出していた。 「ありがとう。」 音読カードを返してもらうと逃げるように自室に戻った。 ドアを閉めた瞬間、なぜか涙腺がせりあがり溢れそうになったがきつく結び直した。机に向かう。 計算ドリルをやらなければいけないはずだがそうはしなかった。 僕はおもむろに「ちいちゃんのかげおくり」のページを開くと、特に何をするわけでもなくこれまでのことをぼーっと考えていた。
アンアンアンソーシャルディスタンス
1週間前から積み上げてきた持ち物をもう一度確認する。パスポートよし、ワクチン証明よし、ガイドブックも持った。 向こうは物価が高い国もあるだろうからもう1つずつティッシュとカップラーメンを足しておこう。 3週間分の荷物が入ったスーツケースは伸縮性の部分がこれでもかと伸びていて笑えてくる。 後は野となれ山となれ。無いものは現地で調達しよう。 そう覚悟を決めて、夜半に向かっていく時間帯に玄関を出た。 コロナウィルスで奪われたものを取り戻しに僕は海外に行く。
ロゴスとしての歴史
大学生になってから授業に出られなくなった。 1コマの授業のために1時間満員電車に潰されるのもめんどくさいとか、飲み会の次の日に起きられないとか繰り返していたらあっという間に留年が決まった。 それでも友だちが周りにいた間はほうけていられたが、いざ5年目が始まり、ぼっちで受ける授業や就活は想像以上に過酷だった。 もう1つの単位も落とせない僕は歯を食いしばり、「東アジアの地域史」に向かった。 退屈だった。 先生は「東アジア地域史」の権威とされているらしいが、権威とされている人ほど概して喋りは下手だし授業は面白くない。しかも初回の授業から1時間半丸々使って説明してきた。 暇だからぼーっとしていた。「初回の授業を途中で切り上げない先生は、学生時代にモテず、輪の中心にいなかった。だが大人になってから話を聞いてくれる人がでてきたのだ。27歳になってから煙草を吸い始め初めての彼女も同じタイミングに違いない。学界では地道な努力が報われ徐々に評価されていき、気づいたらできたのが今の目の前にいる…」 「課題です。ロゴスとしての歴史を書いてきてください。」 絶句した。初回から課題を出す教授は1週間ガリガリ君のナポリタン味より不味いものしか食べてはいけないことになっているはずだ。 「あなたがこの授業を取るまでに至ったロゴスとしての歴史を書いてください。」 言い終わるやいなや教授は教室を出ていき、謎の言葉「ロゴス」に困惑する純朴な大学生が後に残された。 意味が分からなかった。「ロゴスってなんだよ」と「課題出すなよ」が脳内でハウリングする。 友だちがいないので誰かに聞くこともできない。授業を聴いていない自分が悪いのだが誰かを恨みたい気持ちでいっぱいになった。 「ロゴス」で検索しても謎の会社しかヒットしないので諦めてありのままをつらつらと書いた。 留年した経緯。今就活で辛いこと。行き場の無い孤独。この授業を落とせない自分。でも頑張ってるよ今。 書いていたらセルフカウンセリングをしているみたいになった。だんだんと自信が回復し気持ちが高ぶり、これで低評価は無いだろうと思い、課題の送信ボタンを押した。 2回目の授業でも教授は1回目と同じ服を着ていた。僕はまた課題が出たらどうしようと前回よりも緊張して臨んでいた。 「前回の課題を見させてもらいましたが、皆さん非常に素晴らしかったです。中でもよくできていたものをいくつか共有したいと思います。」 言い終わりと同時に教室の大画面に僕のセルフカウンセリングが表示された。驚きで一瞬時が止まった。 「この留年に至るまでの経緯は正直に直接の原因が書かれています。これはロゴスとしての歴史においてとても大切なことです。」 恥ずかしさで顔が割れるかと思った。ロゴスによって生徒のプライバシーがどんどん傷ついていく。お願いだからやめてくれという願いは届かず、先生は10分以上文章の解説をした後でさらにたたみかけてきた。 「強いて言えばこの今につながる部分が弱いです。今の自信とロゴスのつながりが弱いです。」 慎重に積み上げた自信を一瞬で無き者にした挙句どん底に叩きつけるには充分な言葉だった。ジョーが色づいて見えるほど僕は真っ白に燃え尽き、灰になった。その後の授業の記憶は無く、気づいたらまた新しい課題が出て授業は終わっていた。 今までならここで諦めて単位を落としていたがもうその手札は使えない。周りからの声援やサポートの有無に関わらず、僕はもうやるしかないのだ。 「見てろよ、ロゴスめ」 学期末に出た「東アジア地域史」の評価はA+だった。