グラタンメンタル
学生時代、ファミレスでアルバイトをしていた。接客は自分には向いていた。大学では友だちに恵まれず、細々と学校で過ごした鬱憤を晴らすように笑顔を振りまいていた。昼のシフトで入ると決まってパートのおばちゃんに可愛がられた。呼び出し音が鳴ればテーブルに駆け付け、注文を取り厨房に渡す。慣れると機械的に体は動いた。
3年目になると仕事だけでなく受け答えも定型化してくる。世間話も同じことを話す。それは染みついて離れず、他の言葉を探そうとすることもできない窮屈な感覚だ。だけどなんてことはない。そこに安心感を感じるのがおばちゃんたちだ。これが正解だと自分をなだめ続けた。
4年目でもう少しでアルバイトを辞めるころ、40代くらいの夫婦とおぼしき客を対応した。人のよさそうな顔で高級ではないけれど品の良いシャツを着ていた。グラタンとスパゲッティを届け、帰った後で男性がいた席を見やるとグラタンがぐちゃぐちゃに踏みつぶされていた。さっきの人の席かどうかもう一度確認したがやはりさっきのお客さんだった。うちはバルじゃないのに。
拭こうとして見るとテーブルの足と床の隙間に追いやるようにグラタンは挟まっており、拭くのは一苦労だった。ここまできて、もしかしたらさっきのお客さんは夫婦じゃなかったのかもしれないと気づいた。女性にこぼしたグラタンを見られたくなかったのか。拭くのも嫌だったのか。それともその会話になることを嫌ったのか。でも「大丈夫ですか、足元拭きますよ」って言っても変な感じになったら嫌だしなあ。何かできたかなあ。
パートのおばちゃんには黙っていた。きっと興味ないから。
最近、友だちが自殺未遂をした。年に2回くらいは会うし、仲の良い方だと思っていた。話を聞くと職場の悩みがあってアルコール依存症になっていたらしい。全く知らなかった。早くに教えてくれたらとは思うけれど、その葛藤を理解することは難しかっただろう。結局その人がなぜグラタンを踏みつぶすに至るのか、聞けないままだ。どこかに他の選択肢があったんじゃないかと思っても、思うことしかできず自分の無力さを痛感した。ちゃんと向き合えていたら違ったのかな。グラタンも友だちも。
とりあえずパートのおばちゃんからのラインを定型文で置きにいくのを辞めた。もっとこうなんていうか、柔らかく熱くいきたいから。
1
閲覧数: 67
文字数: 979
カテゴリー: 日記・エッセー
投稿日時: 2021/12/29 14:57
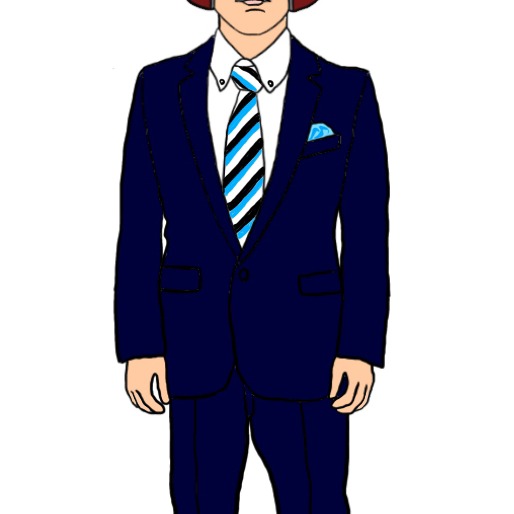
いわごん